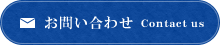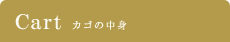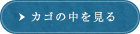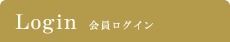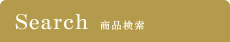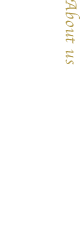東京手仕事」プロジェクト 令和4年度開発商品 中小企業振興公社理事長賞受賞
再生コットンに江戸更紗の技法で染め上げたサステナブルを持ち歩くトートバッグ。
伝統的な美しさ使いやすさにもこだわった逸品です。
今回期間限定で7月22日まで20%オフで販売中です
購入はこちら 
赤色のバッグは合成で制作しております都合、現物とお色味が若干異なる場合があります。
【商品の特徴】
江戸更紗をサステナブルな素材に染め上げて、日本の伝統的な美しさと地球環境へのやさしさを兼ね備えた、
日常生活の中で使いやすいトートバッグを製作しました。
大手ブランドも賛同/採用しているタキヒヨー株式会社の廃棄デニムを原料とした再生コットンブランド
「THE NEW DENIM PROJECT」の生地を表地/裏地ともに採用し、工房で丁寧に染め上げました。
江戸更紗で人気の高い丸紋柄を使用し、落ち着いた配色は、和装時/洋装時どちらでも美しくお使いいただけます。
表地は、13枚の型紙を用いて型摺り染めで丸紋を染めた生地を使用し、
裏地は、引き染めにより紺色に地染めした生地を使用しています。
表地の柄は、フルーツの断面を切ったデザインをモチーフにした江戸更紗定番の丸紋を使用し、
パッケージ(巾着)のロゴも、形紙を用いて型摺り染めで染めます。
男性にもぴったりなデザインとなっています。

【商品の歴史】
更紗は 今から3000年以上も前、インドで発祥したといわれています。語源はジャワ島の古語「セラサ」、インド語で「美しい布」を意味する「サラサー」など諸説があります。
日本で更紗文化が花開くのは江戸時代のことでした。独特の異国情緒が「美しい更紗を何とか染め上げてみたい」という職人の心を揺さぶったのでしょう、職人たちは日本の型染技術を駆使していきました。
染料も、インドと同じものがない中で顔料が使用されました。日本人の手によって作られても、和風にはならなかったのが面白いところです。控えめを美徳とする日本人の感覚ではなく、極彩色を用いて過剰な彩色を施し、独自の花鳥風月を表現していきました。更紗は日本各地に広まりました。
江戸時代の終わり頃、江戸で型染めによる優れた更紗職人が江戸に現れて、江戸更紗の名前が広がっていったと言われています。
江戸更紗は、異国情緒を漂わせながら、しかも深い渋味のある味わいを持つのが特徴で、江戸という風土と粋な江戸人の美意識が表現されて発展してきました。
一方、江戸は神田川をはじめとして、水は硬水です。水中に含まれている鉄分が、染め上げるまでに化学反応して渋い色になります。そのためここに江戸更紗独特の渋味が生まれます。「侘」を感じさせる味わい、「寂」を感じさせる枯れた色合いが特徴です。
各地の更紗は次第に姿を消していき現在、我が国で産地を形成しているのは東京の江戸更紗だけです。
インド更紗から日本独自の技術で生み出された江戸更紗の存在感は、見る人、身に着ける人に感動を与えてくれます。その時代に生きた人々を魅了し、職人たちの技術が昇華していったように、現代に生み出される江戸更紗も、今を生きる人々の中で育まれています。
今や、江戸更紗は世界的にも高い評価を得ています。もともとは着物として、また帯として受け継がれてきたものです。しかし、世の東西を問わず、江戸更紗は さまざまな分野で活用されてきています。タペストリーや椅子の張り地などのインテリア、アクセサリーや生活用品のあらゆる場面で独特の味を出した商品も開 発されています。江戸更紗には限りない可能性があります。
【染の里 おちあい】
創業大正9年、100年続く染工房です。新宿は染物が地場産業であり、現在も50近くの染関連業種が集積しています。
操業から100年着物や帯といった型紙を使用した手染めに拘り、現在も和小物もすべて手染め製造/販売をしております。染の里二葉苑は染物体験や教室も運営し、手染めの製造・販売・体験・教室を運営する総合的染工房として地元に愛される存在をめざしております。館は新宿区のミニ博物館に指定されております。
【受賞歴】
「東京手仕事」プロジェクト 令和4年度開発商品 中小企業振興公社理事長賞受賞
【使用上のご注意】
日の当たる場所にずっと置くと色褪せの原因になります。
【サイズ】
高さ27×幅33×奥行き15cm 約500g
【素材】
綿・牛革